

異動してから仕事が全然うまくいかない…
3ヶ月も経ったのに、職場になじめないのは自分だけ?

異動して間もない頃、ふと「異動後の仕事についていけない」と感じたことはありませんか?
環境が大きく変わり、慣れない業務や新しい人間関係にストレスを抱えるのは決して珍しいことではありません。中には「異動後すぐに辞めてもいいですか?」と本気で悩んでいる方もいるでしょう。
本記事では、異動にまつわるさまざまな悩みや不安に対して、実践的なヒントをまとめています。
例えば「人事異動は何年目が多い?」といった素朴な疑問から、「正社員は異動を断れる?」という働き方に関わる重要なテーマまで、幅広く取り上げています。
さらに、「異動後慣れるまでどれくらい?」と感じている方に向けて、適応の目安や工夫も解説しています。実際、「異動後ミスばかり」と落ち込んだり、「異動後1年たっても仕事ができない」と自己否定に悩んだりする人は少なくありません。
「異動後しんどい」という心の声に、正面から向き合う方法を知ることも、乗り越えるための大きな一歩です。
特に「異動して3ヶ月たっても慣れない」という悩みは、多くの人が経験する“適応途中”の一場面にすぎません。本記事を通じて、自分の現在地を客観的に見つめ直し、必要な対処法や選択肢を考えるきっかけにしていただければと思います。
異動後の仕事についていけない時の対処法

- 異動後すぐに辞めてもいい?
- ミスばかりで悩んでいる人へ
- 1年経っても仕事ができない時の判断軸
- 3ヶ月は慣れないのは普通?
- しんどい気持ちを軽減するには
異動後すぐに辞めてもいい?
辞めるべきかどうかを判断する前に、まずは状況を冷静に整理することが大切です。新しい職場環境に慣れるには、ある程度の時間が必要だからです。
多くの場合、異動直後は業務内容や人間関係、職場文化の違いに戸惑いを感じます。この戸惑いが「自分には向いていない」といった結論を早まらせてしまうことがあります。
例えば、異動から1週間で「もう無理かもしれない」と感じたとしても、それは単に不慣れなだけということもあります。慣れるまでには個人差がありますが、少なくとも1〜3ヶ月ほどは様子を見る人が多いようです。
ただし、身体的・精神的な不調が出ている場合や、明らかにパワハラ・過重労働などが原因でストレスを感じているなら、無理に続ける必要はありません。
このようなケースでは、早めに人事や産業医に相談した上で、退職や再異動を含めた選択肢を検討するのが良いでしょう。
つまり、辞めること自体は決して悪いことではありませんが、「すぐに」というタイミングが本当に妥当かどうかは慎重に判断する必要があります。
まずは、今の悩みが一時的なものか、環境が根本的に合っていないのかを見極めることが重要です。
ミスばかりで悩んでいる人へ

ミスが続くと自信を失いやすくなりますが、異動後のミスは誰にでも起こり得ることです。まず知っておいてほしいのは、「新しい環境に慣れていない時期のミスは、あなたの能力そのものを否定するものではない」ということです。
異動先では、業務フローや判断基準、使うツールなどがこれまでと違う場合がほとんどです。慣れた作業であれば自然にできることも、慣れない場面では判断が遅れたり、確認不足が生じたりします。
例えば、前の部署では上司に確認してから処理していたことが、異動先では「自分で判断して進める」がルールだった場合、最初はどうしても戸惑いが生じます。
その結果、報告のタイミングを逃してしまったり、誤解を生む対応をしてしまうこともあるでしょう。
こうしたミスを減らすためには、業務内容をただ覚えるだけでなく、「この部署ではどんな判断が求められているのか」といった視点で観察し、理解を深めることが効果的です。
また、自分の行動を一度紙に書き出してみると、どこに注意点があるか客観的に見えてくることもあります。
落ち込む気持ちもよく分かりますが、大切なのは「なぜミスが起きたのか」を冷静に分析し、次に活かすことです。周囲からのアドバイスを素直に受け入れながら、少しずつ環境に慣れていけば、ミスは確実に減っていきます。
1年経っても仕事ができない時の判断軸
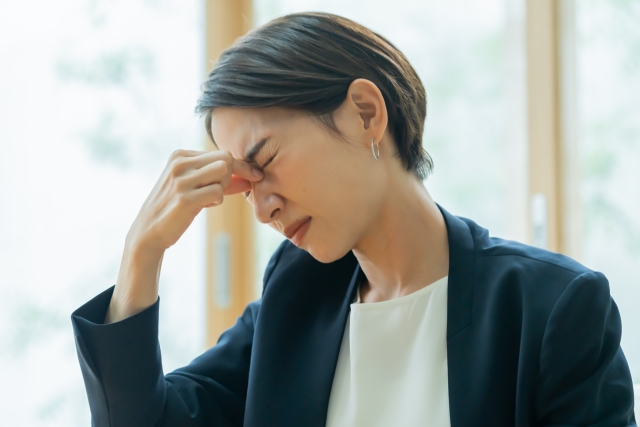
異動から1年が経過しても仕事に自信が持てない場合、見直すべきポイントは「成長の実感があるかどうか」です。
単に成果が出ていないことよりも、「できることが増えてきたか」「前より理解できる業務が増えているか」という視点で自身を振り返ることが大切です。
異動直後は業務に慣れることで精一杯だったとしても、半年〜1年も経てば、ある程度の流れやルールは把握できているはずです。
それにもかかわらず、毎回同じミスを繰り返していたり、周囲との連携が上手くいかない場合には、何らかの要因がある可能性があります。
例えば、上司や同僚の指示が抽象的で分かりにくい、もしくは質問しづらい雰囲気の職場環境であると、学習効率が下がってしまいます。
また、異動先の業務が自分の得意分野とかけ離れている場合、努力しても成果に結びつきにくいという壁に直面しやすくなります。
このような状態が続くと、自信喪失に繋がるだけでなく、評価にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、まずは「業務内容が自分に合っているか」「職場環境に問題はないか」「周囲に相談できる体制があるか」といった視点から、状況を客観的に捉えてみてください。
場合によっては、異動願いやキャリアの見直しも選択肢になります。無理に居続けることで心身のバランスを崩してしまうよりも、「違う形で活躍できる場所を探す」ことも前向きな判断です。
3ヶ月は慣れないのは普通?

異動してから3ヶ月が経っても、職場にうまく馴染めない、仕事がスムーズに進まないというのは、珍しいことではありません。この時期はまだ「適応期間」であり、多くの人が少なからずストレスを感じています。
異動によって仕事内容が大きく変わった場合は、覚えるべきことが多く、一つひとつの判断にも時間がかかります。また、人間関係の構築や職場の文化に慣れることも含めると、3ヶ月という期間は決して十分とは言い切れません。
例えば、社内のルールや専門用語にまだ慣れていない、周囲との会話に緊張してうまく意思疎通ができない、といった悩みを持つ人は少なくありません。こうした環境の変化に対して「時間がかかって当然」と考えることが、気持ちの安定にもつながります。
もちろん、3ヶ月の中で「何も変わらなかった」「まったく業務がこなせない」という場合には、取り組み方やサポート体制を見直すことも必要です。
ただし、それは「あなたが悪い」からではなく、「まだ適応途中である」という前提で向き合うことが大切です。
焦らずに、一つずつできることを増やしていく姿勢こそが、職場での信頼につながります。ミスを恐れすぎず、疑問に思ったことは早めに周囲に確認することで、慣れるスピードも確実に上がっていきます。
しんどい気持ちを軽減するには

しんどさを感じるときは、まず「全部を完璧にこなそうとしすぎていないか」を振り返ることが大切です。異動によって環境が大きく変わると、期待に応えなければというプレッシャーから、自分を必要以上に追い込んでしまうことがあります。
このようなときは、仕事のペースを落とし「できることから丁寧に取り組む」という意識を持つだけでも、気持ちが少し軽くなります。
また、あらかじめ「うまくいかない期間もある」と理解しておくことで、自分へのハードルを下げられます。
例えば、業務内容の理解に時間がかかっていたとしても、先輩に一つ質問できた、前回よりも早く資料を作成できた、など「小さな達成」に目を向けることで、心のバランスが整いやすくなります。進歩が見えると、自信にもつながり、しんどさは徐々に和らいでいきます。
一方で、しんどい気持ちが長く続くときは、誰かに話すことも効果的です。信頼できる同僚や友人、あるいは社内の相談窓口を利用することで、気づかなかった改善策や新たな視点が得られることがあります。
それでも改善が見られない場合は、産業医や外部の専門家に相談することも検討しましょう。気持ちを言葉にするだけでも、整理されて気分が落ち着くことがあります。
頑張ることも大切ですが、それ以上に「自分を守る」ことを忘れずに。しんどさを無理に我慢するのではなく、少しずつ減らしていく方法を探ることが、長く働き続けるためには重要です。
異動後の仕事についていけない理由と原因

- 異動後慣れるまでどれくらい?
- 人事異動は何年目が多い?
- 正社員は異動を断れる?
- 異動で感じるストレスをやわらげるコツ
- スキルギャップと業務の複雑さへの対応
- 異動後ついていけないなら転職・スキル習得も選択肢に
- 異動後の仕事についていけないと感じたときの対応まとめ
異動後慣れるまでどれくらい?
異動後に新しい職場や業務内容に慣れるまでの期間は、人によって差はありますが、おおよそ1〜3ヶ月が一つの目安とされています。
ただし、業務の難易度や人間関係、これまでとのギャップが大きい場合は、半年ほどかかるケースも珍しくありません。
慣れるまでに時間がかかる背景には、「職場文化の違い」や「求められるスキルの変化」があります。
例えば、前の部署では報告・連絡・相談が徹底されていたのに、異動先ではある程度の裁量で動くことが前提になっていることもあります。こうした文化の違いに適応するには、観察力と柔軟な姿勢が求められます。
また、仕事内容が専門的な場合や、新しいツール・システムを覚える必要がある場合は、単純に時間がかかってしまいます。そのため、短期間で結果を出そうと無理をすると、かえってストレスやミスが増えることになりかねません。
慣れるスピードを早めたいのであれば、業務フローを自分なりにまとめる、疑問点はすぐに質問する、といった工夫が有効です。
また、同じ部署の人の動きを観察し、どのような判断や進め方をしているかを把握しておくと、職場の“空気感”にも馴染みやすくなります。
焦らず、自分のペースで少しずつ環境に馴染んでいくことが、結果として安定した働き方につながります。
人事異動は何年目が多い?

一般的に、人事異動が行われやすいタイミングは「入社3年目前後」と言われています。企業によって方針は異なるものの、この時期に異動を経験する人が多いのには明確な理由があります。
3年という期間は、業務を一通り習得し、独り立ちできると判断される頃です。
そのため、会社としては社員にさらなる経験を積ませるために、異なる部署や拠点での勤務を通じてスキルの幅を広げてほしいという狙いがあります。
また、ジョブローテーションを導入している企業では、2~3年おきに異動が組まれているケースも多く、本人の適性を見極めたり、将来の幹部候補を育成したりする目的で異動を実施することがあります。
一方、5年目や10年目といった節目で異動するパターンも見られます。
この場合は、昇進・昇格のタイミングや、大型プロジェクトの始動など、より戦略的な目的を持って異動が行われることが多いです。
このように、異動のタイミングには一定の傾向はあるものの、すべての人が同じ時期に経験するわけではありません。
社内の方針や個人のキャリアプラン、職種によっても変わるため、異動があることを前提に心の準備をしておくと、いざというときに柔軟に対応しやすくなります。
参考:厚生労働省 企業における転勤の実態に関する調査」調査結果の概要
正社員は異動を断れる?

原則として、正社員は会社からの異動命令を断ることはできません。多くの企業では、就業規則や雇用契約に「業務命令による配置転換」や「異動の可能性」が明記されており、それに同意したうえで入社しているからです。
ただし、すべてのケースで絶対に従わなければならないわけではありません。例外的に、異動を拒否できるケースもあります。例えば、「勤務地や職種を限定する契約になっている場合」や、「異動によって家庭生活に重大な支障が出る場合」などです。
具体的には、家族の介護や育児、本人の健康上の理由などで異動が困難な事情があるときは、会社側に相談することで配置転換の見直しや、別の選択肢が提示されることもあります。
また、会社が異動を命じる正当な理由がなく、明らかに不当な目的(例えば報復や嫌がらせ)であった場合、その命令自体が「権利の濫用」とみなされる可能性もあります。
とはいえ、異動命令を一方的に拒否すると、人事評価への影響といったリスクも考えられるため、まずは冷静に話し合いの場を持つことが大切です。
「なぜ異動が困難なのか」を明確に伝え、代替案を提示するなど、建設的な対応を心がけましょう。
つまり、基本的には断れない立場ではあるものの、状況次第で会社と交渉する余地はあります。無理をする前に、正確な情報と冷静な判断を持って対応することがポイントです。
異動で感じるストレスをやわらげるコツ

異動はキャリアの転機でもありますが、それに伴うストレスは決して軽視できません。環境が大きく変わることで、身体や心に負担がかかるケースは少なくないからです。
特に多くの人が感じるのは「人間関係の変化への不安」と「新しい業務へのプレッシャー」です。前の部署で築いてきた信頼関係がリセットされ、新たにゼロから関係を作り直す必要があります。
加えて、業務内容が大きく変わると、覚えることや慣れるまでのストレスも重なります。
例えば、「前はできていたのに、今はミスばかり」という感覚が続くと、自分を否定されたような気持ちになってしまうことがあります。
また、成果が見えにくい初期段階では、周囲からの評価や自分の存在価値について過剰に気にしてしまうこともあります。
こうしたストレスが長引くと、食欲不振、集中力の低下といった身体的な不調を引き起こすこともあります。
メンタル面でも、自信喪失やモチベーションの低下が続くと、うつ症状につながるリスクもあるため注意が必要です。
対策としては、「無理をしない」「1人で抱え込まない」ことが何より大切です。
日々の小さな成功を積み重ねて自信を取り戻したり、周囲に相談してサポートを受けたりすることが、ストレスの軽減につながります。
また、心身の異変を感じた場合は、早めに専門機関や産業医に相談することも選択肢に入れておきましょう。
ストレスは「感じてはいけないもの」ではなく、「うまく付き合っていくもの」と捉えることが、異動後の安定した生活への第一歩になります。
スキルギャップと業務の複雑さへの対応
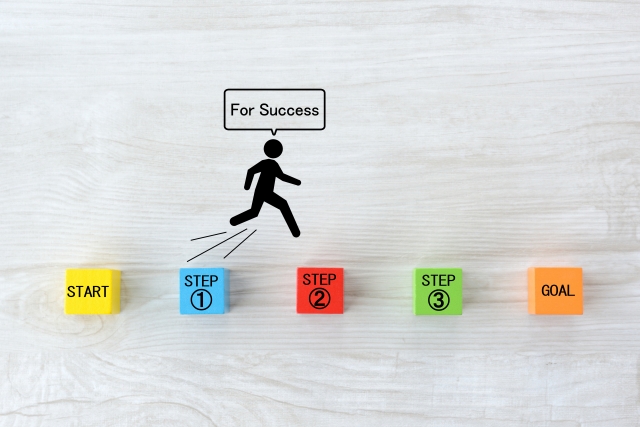
異動後に「これまでのスキルが通用しない」と感じるのは、ごく自然なことです。部署ごとに求められる知識や判断基準が異なるため、これまでの経験では対応しきれない場面に直面することがあります。
まず大切なのは、自分に足りないスキルが何なのかを具体的に洗い出すことです。たとえば、新しい部署でプレゼン資料の作成が求められるのにPowerPointの操作に不安があるなら、「操作スキルの習得」が必要です。
業界用語や専門的な手順が分からない場合は、「業務知識のインプット」が優先されます。
このように明確にしておくことで、焦点の定まった学習や練習が可能になります。一方で、業務そのものが複雑な場合は、一度にすべてを理解しようとせず、「業務を小さく分解する」ことが効果的です。
例えば、「1つの案件の流れ」を最初から最後まで全て覚えるのではなく、「最初の受付対応」「途中の資料作成」「完了報告」といったフェーズごとに分けて覚えると、負担が軽減されます。
また、理解があいまいな部分はメモを残しておき、同じミスを繰り返さないように活用するのも有効です。
さらに、周囲に質問しやすい環境をつくることも重要です。「何が分かっていないのか」が自分でも明確であれば、質問もしやすく、相手も答えやすくなります。
スキル不足や複雑な業務に直面しても、対応の仕方次第で着実に前進できます。完璧を目指すより、「前より少しでも理解できた」と感じられることを重ねていくことが、乗り越える力につながっていきます。
異動後ついていけないなら転職・スキル習得も選択肢に
異動後の職場で「何もできない自分」に自信を失っていませんか?それは、あなたの能力が足りないのではなく、合わない環境にいるだけかもしれません。
そんな時こそ、「書く力」や「発信力」を身につけて副業・転職・在宅ワークの選択肢を増やすという新しい一歩も考えてみてください。
web+ Media School(ウェブタス メディア スクール)は、副業としてWebライターを始めたい方、将来的に起業を目指している方に向けたオンライン学習サービスです。
学びを収入につなげたい人にとって、長期的なサポートと柔軟な学習体制が整っているのが大きな魅力です。
提供されているのは「Webライターコース」と「マイクロ起業コース」の2種類。それぞれのコースでは、専門性の高いノウハウを体系的に学べるだけでなく、学習後すぐに実践へとつなげやすいサポートが用意されています。
たとえばWebライターコースでは、200ページを超える教材や動画コンテンツを使い、SEOライティングの基礎から実践的な案件対応スキルまでを網羅。実際に執筆した記事は、記名記事としてポートフォリオに掲載できるため、仕事獲得にも活かせます。
また、カリキュラム終了後には運営側から仕事の依頼が届くケースもあるなど、収益化のチャンスが豊富です。
一方マイクロ起業コースでは、小規模ビジネスの立ち上げから収益化までのステップを丁寧に学べます。業種に関係なく応用できる考え方をベースに構成されているため、すでにビジネスをしている方にも役立つ内容です。
どちらのコースも「期限無制限」でのサポートが受けられるのが特長です。忙しくて途中で止まってしまっても、時間ができたタイミングでいつでも再開可能。個別のミーティングや毎週のオンラインセミナーもあり、孤独にならずに学びを続けられる仕組みが整っています。
このように、web+ Media Schoolは「今は未経験だけど、将来的に在宅ワークで稼げるようになりたい」「自分の力でビジネスを立ち上げたい」と考える方にとって、実用的なスクールです。
まずは公式サイトから、気になるコースの詳細をチェックしてみてください。
▶︎Web+ Media School 公式サイトはこちら
異動後の仕事についていけないと感じたときの対応まとめ

本記事では、異動にまつわるさまざまな悩みや不安に対して、実践的なヒントを解説しました。
解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。
- 異動直後は戸惑うのが普通であり焦る必要はない
- 最低でも1〜3ヶ月は慣れるまでの猶予期間と捉える
- ミスが増えるのは新しい環境に適応中だからである
- 小さな進歩に目を向けて自己肯定感を保つことが大切
- 心身の不調がある場合は早めに相談や対応を検討すべき
- 異動して1年経っても辛いならキャリアの見直しも視野に入れる
- 異動先の職場文化やルールが合っていない場合もある
- 異動は多くの場合3年目前後に行われる傾向がある
- 正社員でも家庭の事情などで異動を断れるケースがある
- 異動後のストレスは環境変化による一時的な負担が原因
- スキルギャップは小さく分解して対処するのが効果的
- 周囲に質問しやすい雰囲気作りも早期適応のカギとなる
- 辞めるか迷ったときは一度状況を客観的に整理する
- 相談できる人や社内の支援体制を活用することが重要
- 転職やスキル習得も前向きな選択肢として検討してよい
異動後の仕事についていけず、不安やプレッシャーに悩んでいる方は少なくありません。特に、人間関係や業務の変化に戸惑うタイミングでは、その悩みが深くなりがちです。
こうした悩みに向き合うには、「自分にとって合っている仕事は何か?」「このまま続けるべきか?」を考えることが大切です。そして、もし今の職場が合わないと感じたら、スキルを磨いて環境を変えることも一つの手です。
web+ Media School(ウェブタス メディア スクール)では、Webライターや起業を目指す人のための実践型学習サービスで、添削無制限・全額返金保証・全国どこからでも学べるという柔軟さが特徴です。未経験からでも「書く力」「発信する力」が身につき、転職や副業への第一歩を踏み出せます。
異動後のストレスを抱え続けるのではなく、「あなたらしく働ける場所」へと歩み出してみませんか?
自信を持って次のステージへ進みたい方は、web+ Media Schoolの詳細をチェックしてみてください。今の悩みを、未来の成長に変えるチャンスです。

